 住宅ローンの基礎
住宅ローンの基礎 DH住宅ローン指数について
住宅ローン金利は、数多くの銀行が独自に設定します。もしかすると銀行ごとに違いがないと誤解されている方もいるかもしれませんが、調べていただけるとわかると思います。 銀行ごとに、金利はかなりの違いがあります。それは、1,300社も超えるという住...
 住宅ローンの基礎
住宅ローンの基礎 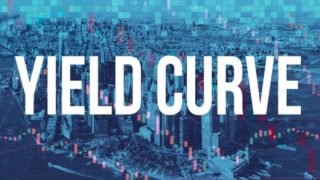 住宅ローンの基礎
住宅ローンの基礎 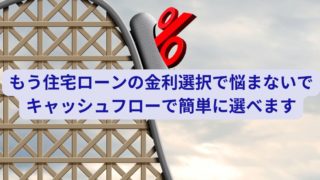 住宅ローンの基礎
住宅ローンの基礎  住宅ローンの基礎
住宅ローンの基礎  住宅ローンの基礎
住宅ローンの基礎 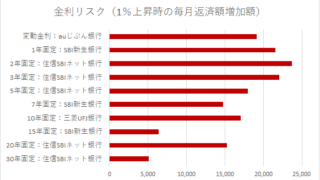 住宅ローンの基礎
住宅ローンの基礎  住宅ローンの基礎
住宅ローンの基礎